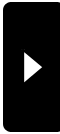2017年12月08日
ベルテント(Sibley 500)内部用の照明 第二弾

今回新しく作った照明です。
ちょっとレトロな感じになったと思いませんか?

この写真は、ベルテント(Sibley 500)内部用に以前作ったライトですが、先日のキャンプで壊れてしまいました。
光の向きを自由に出来るデザインにしたのですが、向きを変えるとき、先端を持ちすぎ、電球ソケットの付け根が割れてしまいました。
そこで新しい照明を作ることにしましたが、壊れた照明の電球(LED)とスイッチは利用して作りました。
前回の経験で、全体の照明は電球の向きを変える必要がないこと、テーブルに向けるスポット電球を下に向ける部品があることを知り、よりコンパクトにシンプルに作ることにしました。

乳白の電球(LED 1.2W)が一番似合う気がします。
上の小さな電球は0.5W(LED)の常夜灯です。
常夜灯のソケットはゴムではなく防水効果がないため、他のソケットのゴムを追加して防水効果を上げています。
寝るときに眩しくないよう、上側に取り付けました。

透明電球(LED 1.2W)取り替えるとずいぶん印象が変わります。

天気が悪いときや寒い季節はテント内で食事をします。
そんな時は普通の電球をを1個外し、スポット電球(LED 3.2W ズーム機能あり)に取り替えます。
この時、スポット電球だけでは真横を向いてしまうので、「ムサシ RITEX 【口金直径17mm LED電球専用】 可変式ソケット 屋内用 DS17-10 防水ではないので注意」を使って下に向けます。
角度が調節出来て便利です。
真夏で天気がいい日以外スポット電球を取り付けた状態が標準です。

同じく透明電球とスポット電球の組み合わせです。

常夜灯の反対側には切れ込みを入れ、テントのポールに取り付けられるようにしています。
黒いベルトは長めのマジックテープです。
ポールに巻いたベージュのテープは何周も巻いています、下にずり落ちないためです。
これは前回と同じです。
以下は作り方の説明です。

変成シリコーンシール(以降シリコーン)で固めて作っていますので、シリコーンが固まった後剥がせるポリプロピレンのシートの上に電球ソケットを並べ、シリコーンで仮押さえしています。
この時、最後に切り込みを入れるソケットとソケットの間に電線が来ないように固定します。
最初は白のシリコーンで作っていましたが、仕上げはベージュのシリコーンを使っています。

1つ前の写真の状態で固まったあと、反対側もシリコーンで固めます。
最初に固定したとき電球ソケットは水平ではありません。
電球が少し上を向くようソケットの電線を反対から出し直します。

ソケットの電線とスイッチ側の電線の繋ぎ目はこんな感じです。
スイッチは3個あれば足りますが、以前の照明で6個使い、減らすのが大変なのでそのまま使いました。
1個づつ単独で点けられるので明るさ調節には便利です、

テントのポールにポリプロピレンのシートを巻いて、その上にシリコーンを塗ります。

固まった後、2個の部品を組み合わせます。
この時、特に電線の位置を常夜灯側に寄せます。

この写真はシリコーンで塗り固め終わった状態ですが、少しずつ塗り足しながら整形しました。
最初にポールに塗ったシリコーンの要らない部分は切り落としています。
テントの中の写真は、次にキャンプに行くまでお待ちください。
先日のキャンプでベルテント(Sibley 500)が雨漏りしました。
その後、クリーニングと撥水を専門業者さんにお願いし、雨漏りしないことを期待していますが、今回の照明で使用する可変式ソケットはまったく防水性がありません。
電球はゴムのソケットでかなり安全だと思いますが、一カ所でも危険なところがあるので、コンセントに取り付ける漏電ブレーカーを使うことにしました。
漏電ブレーカーを使わない場合、そして特に結露の発生すやすいテントの場合、電球とソケットの隙間、可変ソケットの可動部分、危険な所はすべてシリコーンでシーリングすることをお薦めします。
漏電ブレーカーは電気器具が漏電した場合、感電を避けることができます。
2018年1月5日追記
年越しキャンプに行ってきました。
照明の使い勝手は、設置時間も掛からず、常夜灯も眩しくなく非常に良かったのですが、、、、
設置には、最初に電球を取り付けますが、スポット電球の可変式ソケットをねじ込んだとき、内部に埋め込んだ電球ソケットの半田付けが取れてしまい、1灯分が使えなくなりました。
今回の照明を作る原因になった、以前の照明が折れた原因と同じ場所で、電球ソケットの作りの悪さが原因のようです。
今回はスポット電球を1個ずらし、1個の電球がない状態で問題なく過ごせましたが、作ったばかりの照明が、部品の問題で壊れたのは腹立たしいです。
壊れた1灯分は、電球ソケットを交換し何とか修理できそうです。