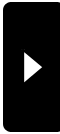2005年12月01日
ちびストーブのメンテ?
先日のキャンプでは、帰りギリギリまで薪を燃やして、燃え残りの燠を水に浸けて無理矢理消しました。
ストーブの底に入れてある灰は、水に流れてしまったので、次回使うのに灰がありません。
私は理由を良く知りませんが、ストーブの底に灰、または砂を入れて使うように説明書に書いてあります。
想像するところ、ストーブの底の保護と地面の芝生などの保護には役に立ちそうです。
ちびストーブには、上部に炭使用時使う器が付いています。
薪ではなく炭を使うときはストーブの上部にその器を入れて使います。
帰った後、そこに炭を入れ火を熾します。炭や豆炭用の火熾しに持ち帰った濡れた消し炭を入れ、ストーブに乗せておくと、下の炭の熱で、上の消し炭が乾きます。
乾いたら下の器に入れ、上には新たな濡れた消し炭を乗せます。
これを1日繰り返すと、必要な程度の灰が下に溜まります。
(薪が杉だと、ここまでの消し炭はできません、広葉樹の薪だと大量に溜まります)
今日は1日パソコンに向かう仕事をしていたので、これを実行しました。
薪を最後まで無駄にしない、次に使うためのメンテナンスだと言いながら毎回実行していますが、実は焚き火をしていると同じ感覚なんです。炭が赤くなり、灰になっていく過程が焚き火と同じに感じる、こんな物好きは他にはいませんね?
ストーブの底に入れてある灰は、水に流れてしまったので、次回使うのに灰がありません。
私は理由を良く知りませんが、ストーブの底に灰、または砂を入れて使うように説明書に書いてあります。
想像するところ、ストーブの底の保護と地面の芝生などの保護には役に立ちそうです。
ちびストーブには、上部に炭使用時使う器が付いています。
薪ではなく炭を使うときはストーブの上部にその器を入れて使います。
帰った後、そこに炭を入れ火を熾します。炭や豆炭用の火熾しに持ち帰った濡れた消し炭を入れ、ストーブに乗せておくと、下の炭の熱で、上の消し炭が乾きます。
乾いたら下の器に入れ、上には新たな濡れた消し炭を乗せます。
これを1日繰り返すと、必要な程度の灰が下に溜まります。
(薪が杉だと、ここまでの消し炭はできません、広葉樹の薪だと大量に溜まります)
今日は1日パソコンに向かう仕事をしていたので、これを実行しました。
薪を最後まで無駄にしない、次に使うためのメンテナンスだと言いながら毎回実行していますが、実は焚き火をしていると同じ感覚なんです。炭が赤くなり、灰になっていく過程が焚き火と同じに感じる、こんな物好きは他にはいませんね?
Posted by ADIA at 21:40│Comments(0)
│雑記